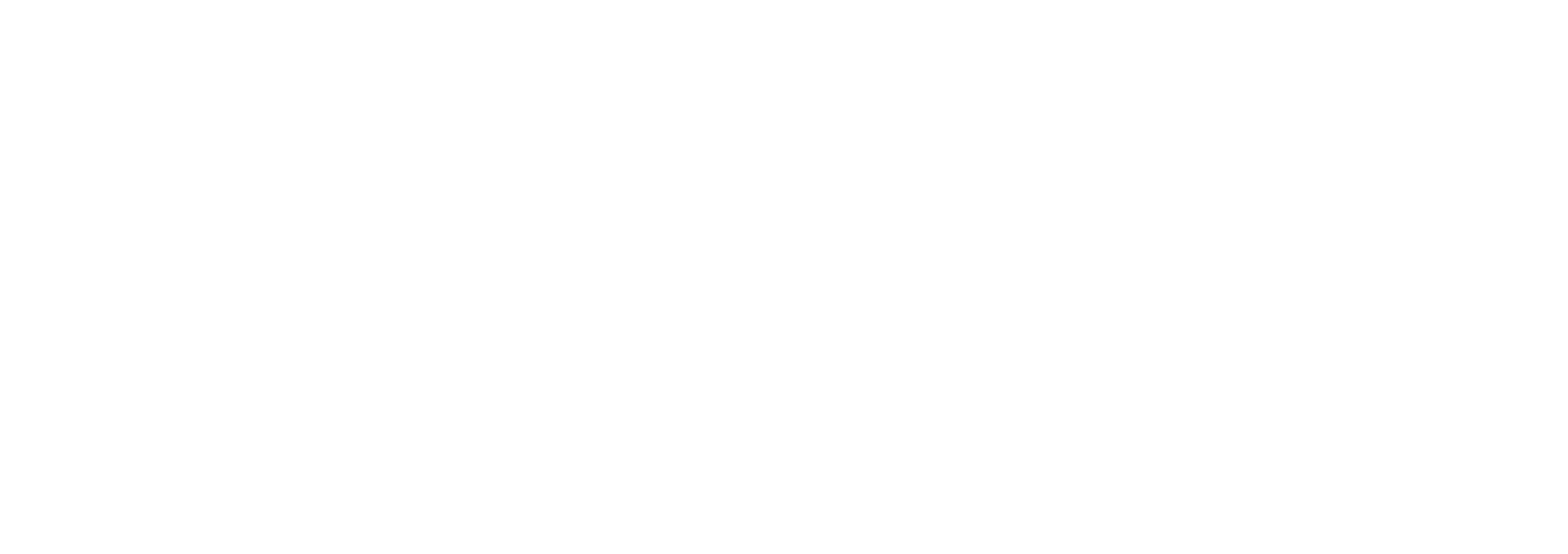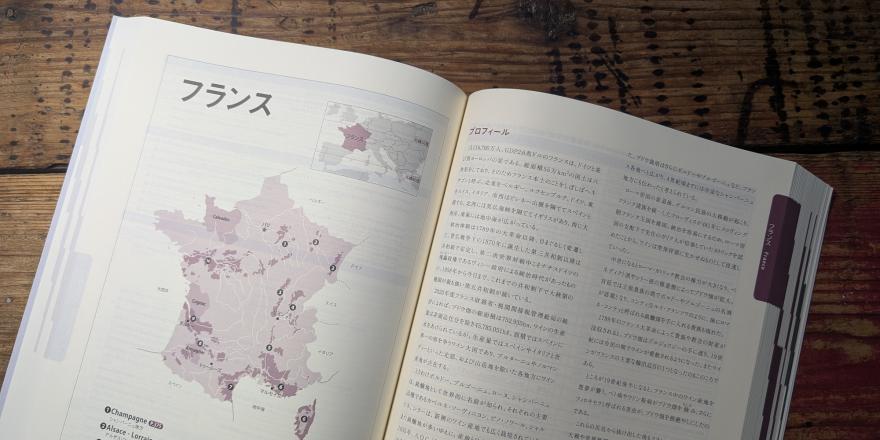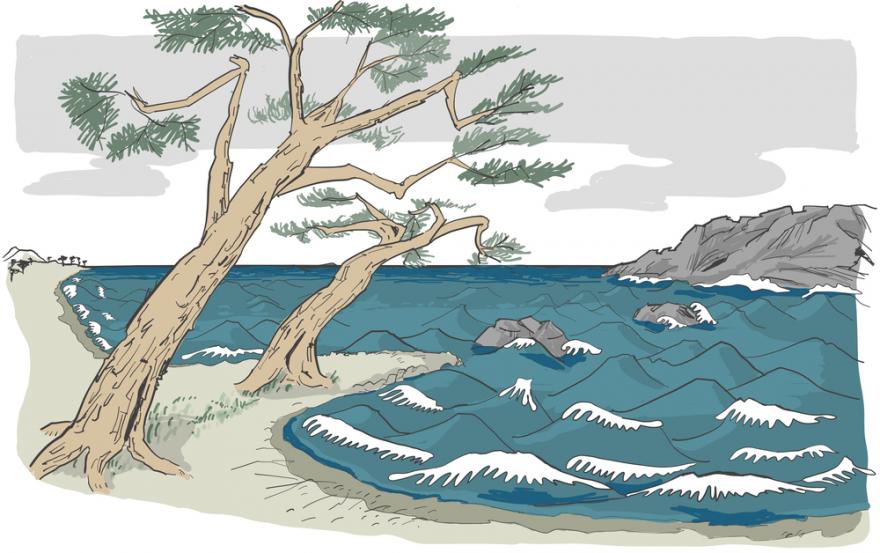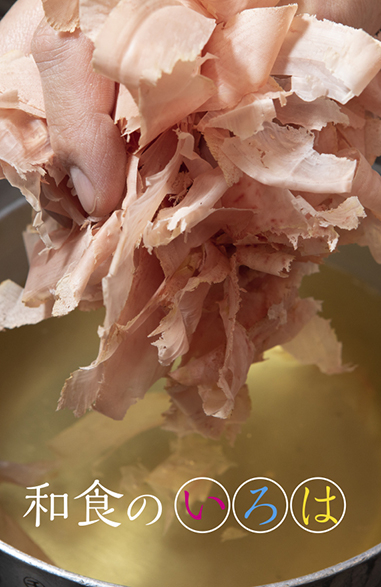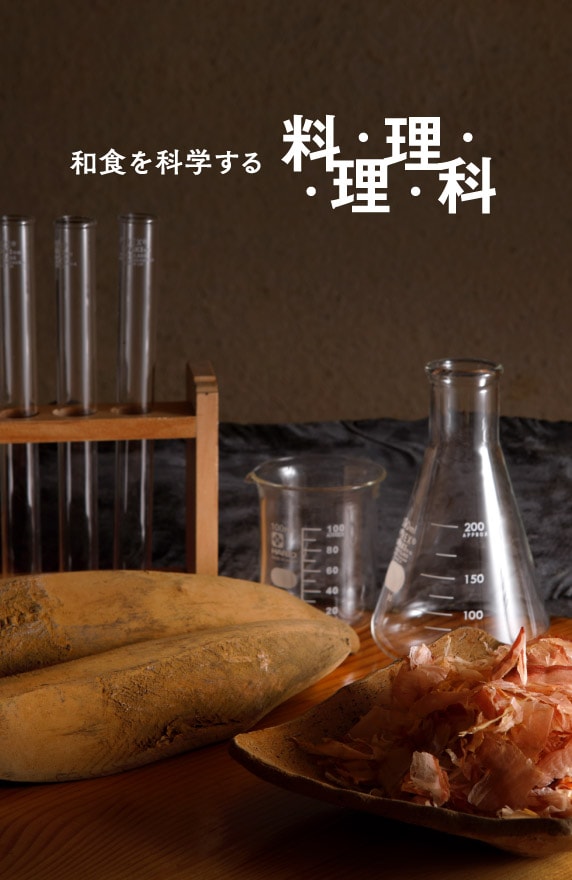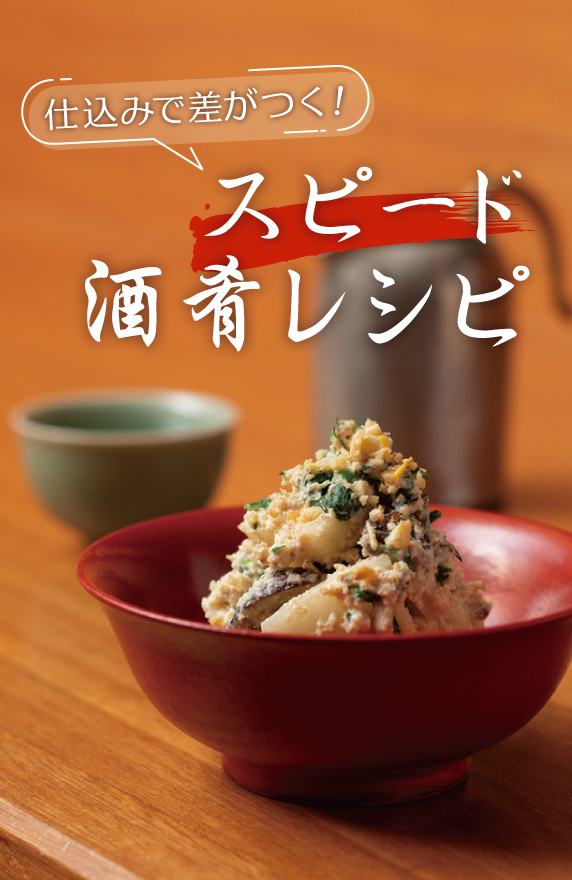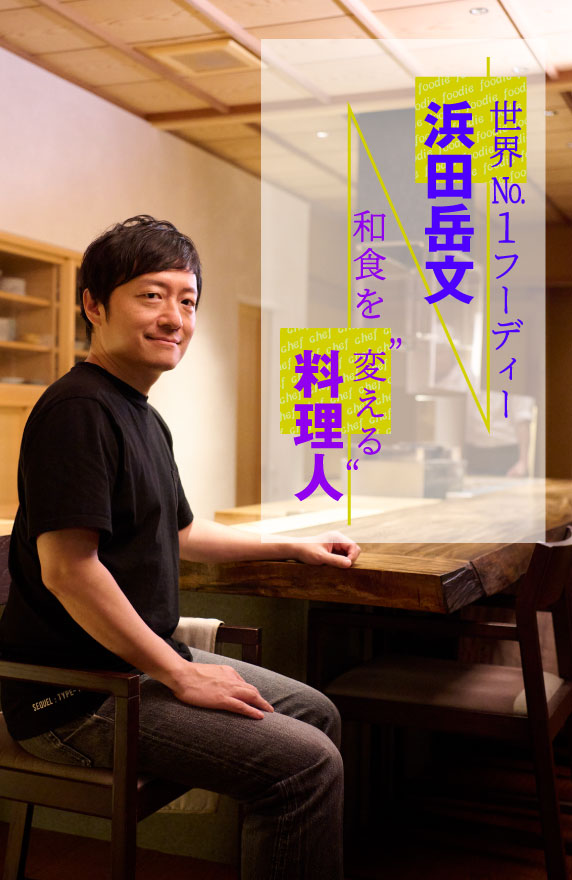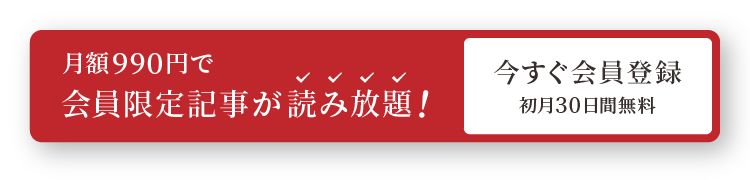【最終回】料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.17三次試験・サービス実技対策
ソムリエの松岡正浩さんに学んできた「料理人のためのソムリエ試験対策」も、いよいよ最終回を迎えます。今回は、三次試験で実施されるサービス実技について。当日の流れや具体的な手順、押さえておきたいポイント、緊張の中で力を発揮するための心構えまで丁寧に解説していただきます。受験本番に安心して臨むための実践的なアドバイスが満載です。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地『空心 伽藍堂』シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『空心 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
「料理人のためのソムリエ試験対策」も最終回となりました。今回は、三次試験として行われるソムリエ呼称のサービス実技についてお伝えします。
この実技試験は私が受験した20数年前から赤ワインのパニエ抜栓、デキャンタージュ、ワインのサービスという流れでした。
会場入りから試験開始まで
試験会場到着
会場入りし、指定された更衣室にて制服に着替えます。レストランやホテルの制服の方、割烹着、CAの制服、スーツの方などさまざまです。仕事着であれば良いので、最近はTシャツにエプロンというカジュアルな受験者も増えていると聞きます。
料理人の方は、白衣やコックコートで挑みましょう。試験官に「料理人の方も頑張っている」と思われた方が好印象です。
所定の場所で待機した後、係の方の案内で実技会場に向かいます。実技は6人一組(地方会場は2〜4人の場合あり)で、受験番号順に行われます。
実技会場入り
手荷物を所定の場所に置き、指定された順に並びます。
正面に数名の試験官が座っています。多くの場合6人の受験者に対して3名の試験官、近くの試験官をお客様と見立て、手前に並んだ会議用の細長いテーブルの一角で実技を行います。ワインやデキャンタ、グラスなどの備品は部屋の後ろまたはサイドのテーブルに準備されています。
試験開始
順番に受験番号と氏名を言い終えると、試験官からお題が出されます。そして、「はじめてください」の掛け声と共に受験者それぞれのペースで実技を始めます。実技の持ち時間は7分。
ここ数年のお題は、「注文された(指定された若い)ボルドーの赤ワインをパニエに入れてプレゼンテーションし、そのまま抜栓、その後デキャンタージュする」というものです。 そして、ソムリエ協会のHPにも記載があるように、2022年度より、角トレイ(345㎜×475㎜)の中で全ての実技を完了させるようになりました。トレイからパニエや下皿等がはみ出してしまうと減点になります。
サービス実技の基本的な流れ
① 注文された(指定された)ワイン名、ヴィンテージを復唱。
② ワイン置き場に向かい、銘柄が上になるように「丁寧に」ワインをパニエに入れて、テーブルに戻り、ワインをプレゼンテーション、ワインが正しいことを確認してもらう。
③ ワイングラス、デキャンタ等、必要備品を取りに行く。
④ ワインをパニエに入れたまま抜栓。
⑤ パニエに入ったワインを少量自身のグラスに注ぎ、テイスティング。
⑥ デキャンタージュする旨をその理由と共にお客様に伝え、デキャンタージュを行う。
⑦ お客様用のグラスにワインをサービスする。
⑧ 「終了しました」と一言添える。
⑨ 指定された通りにワイン、備品を片付けて終了。
サービス実技のポイント
実技の詳しい手順は、協会のDVDやYou Tubeの動画等を見ていただくとして、注意点とポイントをお伝えします。
誰もが緊張した中での実技
想像以上に緊張した中で実技を行うことになります。その緊張した中でいかにいつも通り、練習した通りに進められるか、ここに尽きます。
大きな声で、ゆっくりハキハキと
数人が一斉に実技を行うので、大きな声でゆっくりとハキハキ話すことが大切です。事前に試験中の「セリフ」を想定し一字一句まで決めて、何度も練習しましょう。さらに、緊張するとうまく話せなくなる方は一つの方法として、自分の話す内容を録音して、繰り返し50〜100回ほど聞きましょう。そうすることで文章を覚える以上にテンポまで体に馴染むため、自然と流れるように言葉が出てくるようになります。
特にワインの名前ははっきり繰り返しましょう。
「ありがとうございます。シャトー・タサン(近年はこの銘柄であることが多い)の◯◯年でございますね」という感じです。注文を受けた時に確認することがサービスの基本です。
試験官がお客様という想定ですが、どう見ても座っている場所も試験官でしかありません。少し離れた試験官を意識し、目の前にお客様がいるという想定で実技を行います。試験官はデキャンタージュの了解等の応対はしますが、実際に受験者が試験官の前に出てワインのサービスを行うわけではありません。
若いワインのデキャンタージュ
お題としてここ数年出題が続いている「注文されたワインに即したサービス」が求められた場合(「十数年以上前の古いワインとしてサービスしなさい」ではない場合)は、迷わず「若いワインを空気に触れさせて開かせるためのデキャンタージュ」で進めましょう。ワインは予算の関係もあり、現行ヴィンテージの若い赤ワインが準備されます。
「若いワインであるため、空気にふれさせることで香りや味わいを開かせる」といった旨を試験官に伝え、デキャンタージュの了解を得ます。若いワインと言っているのですから、澱が無い想定です。ワインはボトルから全てデキャンタに移しきりましょう。
澱のないワインをボトルに残す理由は全くありません。
緊張した中で、多くの料理人にとって慣れないデキャンタージュです。澱のある想定にして、少しだけ残すというデキャンタージュを実行するよりも、すべてを移し替えるほうが簡単で、ミスをする確率が圧倒的に下がります。
例えば2018年(7年前)のような試験的に微妙な年代のワインが出題されたとしても、迷わず全て移し替えて、「澱がございませんでしたから、最後の一滴までお楽しみいただけます」などと一言添えれば、私なら100点をつけます。だって、デキャンタージュした本人が澱はないと確認しているのですから。
「古いワイン」がお題になった時もほんの少しだけ残せばいい
デキャンタージュのもう一つのパターン、私が受験した時代のように20~30年ほど熟成した古いワインがお題となった場合は「澱を取り除くためのデキャンタージュ」を行う必要があります。
一般的には、ボトルの肩の部分を下からライトで照らし、澱の動きを目視しながら、澱がデキャンタに入らないように注意してワインを移し替えます。
ただ、試験で実際に準備されるワインは若いもので澱などなく、デキャンタージュする前にライトを付けて、ボトルの肩を通して光を「見ている振り」をするだけで十分です。ここに意識を向けず、ワインを注ぐことに集中する方がうまくいきます。
そして、この場合も理想的には1cm以上ワインを残さないことです。イメージとしては全部注ぎ切るつもりで、最後にほんの少しだけ残す。この「ほんの少し」の感覚をマスターすることが、古いワインがお題のデキャンタージュで最も上手くいく方法であると思います。
デキャンタージュの最中に頭が真っ白になってしまったら、減点覚悟で全てのワインをデキャンタに移してしまいましょう。ワインをたくさんこぼしてしまったり、残し過ぎてアタフタするくらいなら、何も考えず注ぎ切った方が試験官の印象は良いと思います。まぁ、いくらこぼしても、多く残してしまっても、その程度では合否に影響はありません。
心構えと実技試験の実情
自分のペースを守り、細かいミスを気にしない
複数人が同時に実技を行うため、他の受験者のセリフや動きが気になるものです。ですが、惑わされないように心がけ、自分のペースで進めましょう。
また、細かいミスは一切気にしないことです。下皿を忘れた、ライトを付け忘れた、テイスティングや片付けの手順を間違えた等、些細なミスは起こりうるものです。三次試験的には多少減点かもしれませんが、この細かいミスで動揺し、大きな失敗をしてしまうことの方が問題です。
満点、完璧を目指す必要はない
試験官は、立ち振る舞いやソムリエナイフの持ち方を見ただけで、その人が現場でワインをサービスしているかどうかがわかります。そして、実技試験は穏やかな減点方式です。完璧を求める必要はありません。
二次試験のことを思い出してください。皆さんのテイスティングは完璧でしたか。中にはブドウ品種の正解がゼロで突破された方もいらっしゃるでしょう。特に三次の実技試験は幾多の失敗を重ねても、合格ラインを下回らないようになっています。
ですから、料理人としてワインの扱いに慣れていないことを認めた上で、いかに丁寧に実直に進められるかが勝負です。
また、「平常心で臨みましょう」と言いたいところですが、誰もが緊張でガチガチになります。その極度の緊張感の中で実技を行うことになると覚悟しつつ、その中でうまくできると信じ、試験一週間前くらいからはイメージトレーニングも合わせて行ってみてください。
受験報告を読む
この実技試験に関しても、「ちょっとまじめにソムリエ試験対策こーざ」に過去数年分の受検報告がアップされています。実際に受検した人の生の声から試験の流れを把握し、さらに臨場感、緊張感まで共有することができれば、試験本番も落ち着いて臨めるはずです。
実技で落ちる人はほとんどいない
ソムリエ協会の役員で当日試験官を務める友人、知人が何人かいますが、その誰もが「実技で落とすことはほぼない」と口を揃えます。例えば、ボトルを落として割ってしまい実技続行不可能というレベルの失敗でもない限り、不合格になるまで減点されることはないと聞きます。
試験官は料理人の皆さんが日常的にワインのサービスを行っているとは思っていません。ですから、無理に取り繕おうとせず、できることをひとつひとつ丁寧に行い、途中で失敗を重ねても、あきらめず最後までしっかりとやり通すことができれば必ず大丈夫です。
合格してからが本当の修業です。
約一年間、お疲れ様でした。久しぶりに本気で勉強したという方も多いのではないでしょうか。
料理人の皆さんならご理解いただけると思いますが、料理と同じように、ワインもソムリエ呼称を取得してからが本当の修業です。この合格は、広大なワインの世界に足を一歩踏み入れたに過ぎません。
これからどのようにワインと向き合っていくか。それこそがこれから最も大切なことなのですが、この話はまたいずれどこかで。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから。
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
フォローして最新情報をチェック!