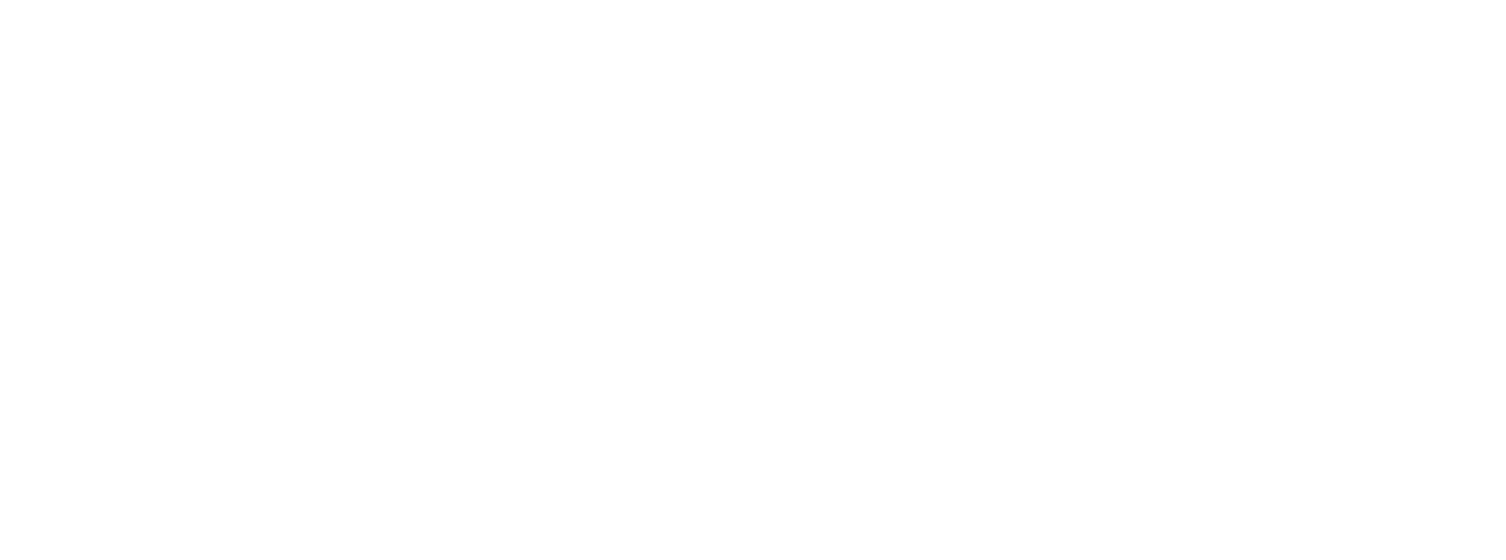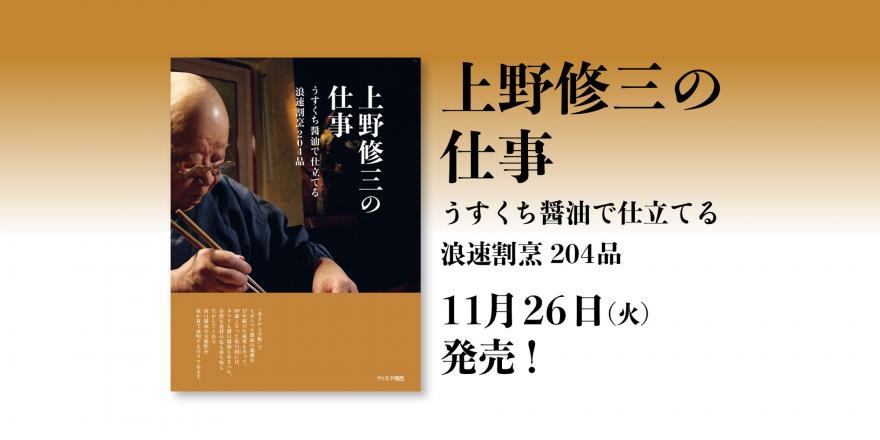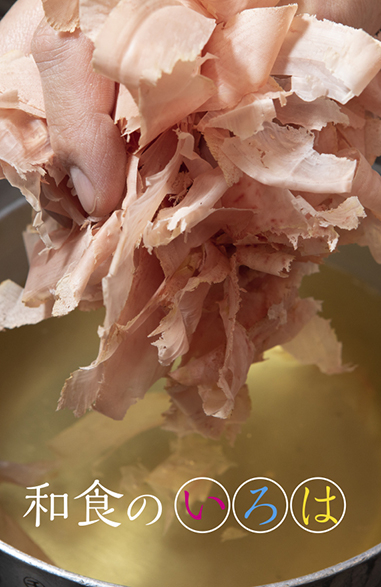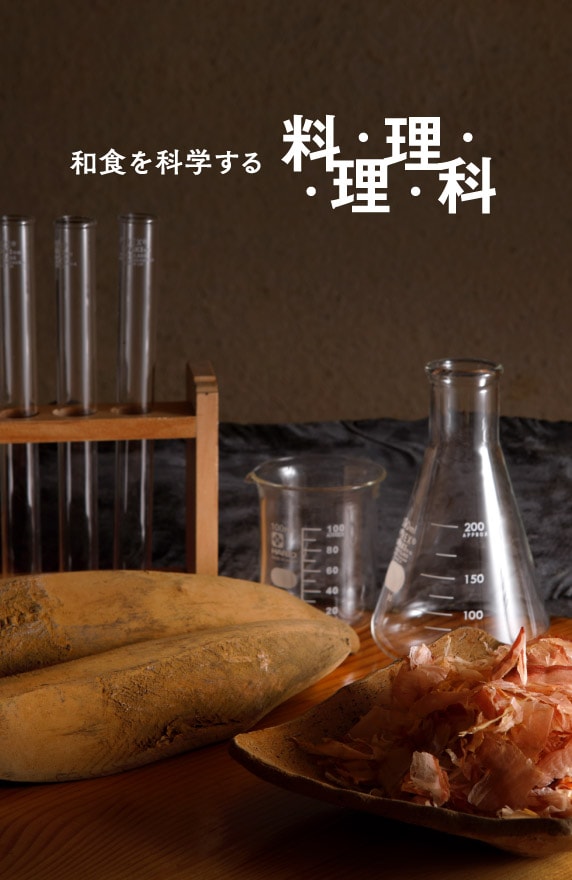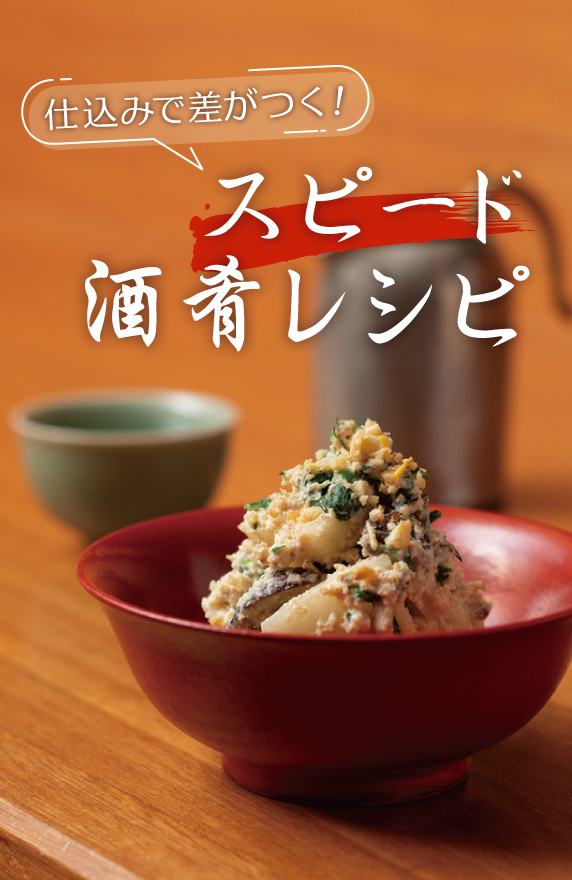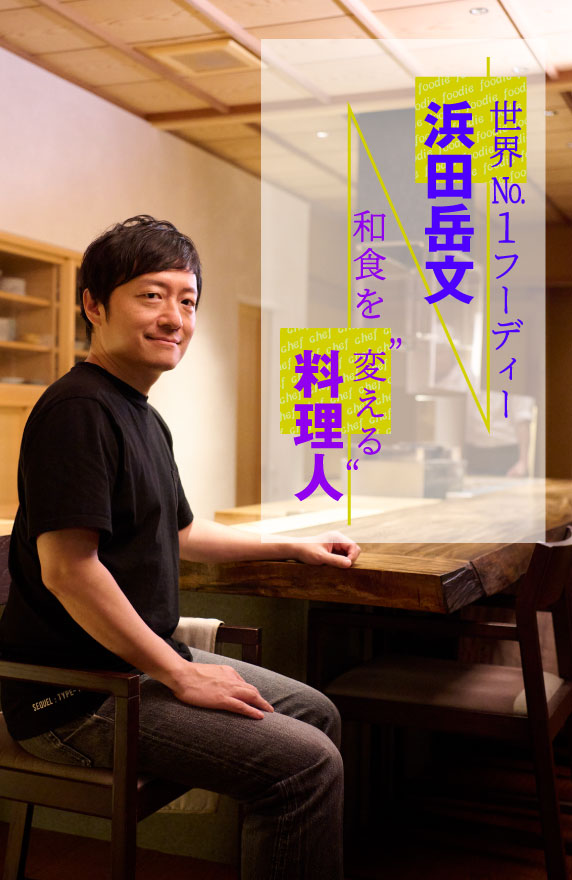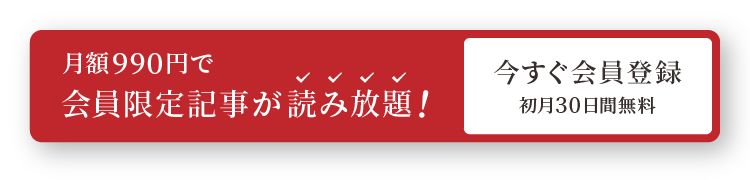【レシピ付き】皮付き針イカを丸ごと味わう、淡口仕立ての2品
晩秋から初冬の針イカは、「皮付きで食べてこそ旨い」と上野修三さん。柔らかいゲソも捨てがたいからと、皮付きの胴身の中に隠して、割烹らしい2品を仕立てました。霜降りだけでほぼ生の持ち味を生かした一品は、2種の吉野酢にワタも使って。イカ飯風の白扇揚は、大根おろしにイカ墨パウダーをのせ、淡口仕立ての天つゆで。一口で針イカを丸ごと楽しませる創意工夫は、90歳になっても健在です!
上野修三(うえのしゅうぞう):昭和10年、大阪・河内長野に生まれる。ミナミでの修業時代を経て、1965年、『㐂川(きがわ)』を創業。なにわの伝統野菜を発掘するなど、大阪らしい料理を追求し、浪速割烹のカタチをつくる。60歳で開店した『天神坂上野』は伝説の割烹として名を馳せた。2024年11月に「上野修三の仕事 うすくち醤油で仕立てる浪速割烹204品」(クリエテ関西)を上梓するなど、御年90歳ながら、なにわの食文化を綴る随筆家として活躍中。
ゲソを皮付きの胴身に隠し、ワタも墨も工夫して
関西ではコウイカ、関東ではスミイカ。背に甲羅を持つ扁平のイカやけど、9月末から赤ちゃんの新イカが出てきて、冬場には成イカになる。そのちょうど間、晩秋から初冬の針イカが今回の主役でおます。
実はこの2品、新イカで昔よぉ作っていた料理のアレンジ版ですねん。体長8㎝くらいの赤ちゃんイカが、私ゃ大好物でネ。さっと霜降りして、小さな胴身にゲソだけ叩き入れてお薦めしたもんだす。初々しい味わいやから、粒ウニと淡口醤油に卵黄、昆布だしで加減したタレを添えてネ。
針イカは体長15㎝くらいになるけど、身も皮もまだまだ柔らかい。皮付きのまま霜降りし、コリッとした食感を生かしたのが1品目だす。しっかりとした持ち味やから、ウニの力を借りずに、ワタ入りの酢と淡口吉野酢でお薦めしておくれやす。
このサイズなら、ゲソ入りの胴身を揚げても旨いんちゃう?と発想が広がって。蒸した道明寺粉を合わせて、イカ飯風にしたんやけど、どないだす? 墨袋も捨てまへんでぇ。湯煎すると水気が飛んで、イカ墨パウダーになりますねん。味が凝縮して、なかなかオツなもんだっせ。この白扇揚は淡口醤油の天つゆでお薦めしますが、添えた大根おろしにパラパラ-ッと振りかけたら、ちょっとユニークでっしゃろ。
皮からワタ、墨袋まで、食べられるとこは全部使いましたでぇ。胴身とゲソを合わせた仕立てやから、一口で針イカを丸ごと味わえることになる。大阪らしい面白みもあって、始末もええ2品になりましたわ。

ゲソ詰め針烏賊——2色の吉野酢は淡口醤油+柚子果汁と、ワタ入りで
江戸の頃のハナシやろうけど、「大阪に行ったらイカ刺しを食べるべし」という評判が立ったそうだす。このイカは、おそらく大阪湾で揚がるコウイカ。独特の甘みが好まれたんでしょうな。
けどネ、私ゃ、食味の上では針イカに軍配を上げますな。皮付きでさっと湯引きしてみなはれ。コリコリッとした食感は、成イカにはないもんでっせ。柔らかいゲソがまた旨くてネ。吸盤だけは歯に触るから取り除いた方がええけど、これも皮付きのままがよろしいな。
とはいえ、割烹でゲソをそのままお出ししては、恰好がつかへん。それなら胴身の中に隠してしまえ!ってのが、私の考え。叩いて胴身に詰めるのに、量がちょっと足りなかったので、つなぎに山芋とろろも混ぜましてん。桂むきにしたキュウリでくるんでから胴身に入れたら、歯ざわりもよろしいな。
残ったワタは、蒸してから裏漉しし、土佐酢と合わせてワタ酢に。これだけでも充分やけど、針イカそのものの持ち味を生かすなら、もう一種。ここは、淡口醤油の出番やね。みりんと合わせてひと煮立ちさせたところに、柚子果汁を流し入れたら、爽快さも加わってええ塩梅だす。
ゲソ詰め針烏賊のレシピ
【材料(6人前)】
<ゲソ詰め針烏賊>
針イカ……360g(2ハイ)
昆布だし……適量
山芋……100g
キュウリ……適量
昆布・塩・ゴマ油・水溶き吉野葛……各適量
●ワタ酢(作りやすい量)
│針イカのワタ……5g
│土佐酢※……100ml
│水溶き吉野葛……適量
●淡口吉野酢(作りやすい量)
│淡口醤油……50ml
│みりん……15ml
│水溶き吉野葛……適量
│柚子果汁……40ml
浜防風……適量
※土佐酢(作りやすい量)
カツオ昆布だし720ml・米酢1080ml・淡口醤油180ml・砂糖180g・昆布1枚を鍋に合わせ、ひと煮立ちさせる。追いガツオして冷めたら漉す。
【作り方】
<ゲソ詰め針烏賊を作る>
- ①
- 針イカは甲羅を抜き取り、ゲソ付きの内臓を引き出す。ゲソは吸盤を取り、胴身の中を掃除して、どちらも昆布だしで霜降りする。
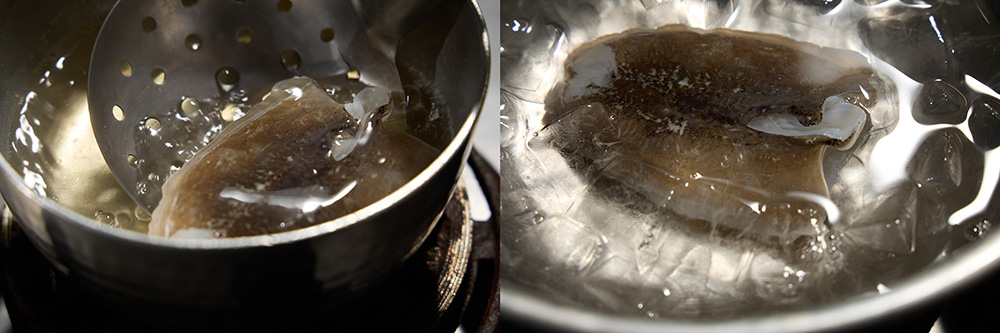
- ②
- 山芋は7割を蒸して裏漉しし、残りはすりおろして合わせる。
- ③
- ①で霜降りしたゲソを叩き、②と混ぜ合わせる。

- ④
- 針イカの胴身の長さに合わせてキュウリを桂むきし、昆布立て塩に5分ほど浸しておく。
- ⑤
- ④の水気を取り、③の半量弱を巻く。巻き終わりから少し先で切り離す。①の胴身に差し込み、トントンと落とすようにして奥まで入れる。胴身の中に隙間ができないよう、残りの③を詰めて端を閉じる。冷蔵庫で30分以上置いて落ち着かせる。
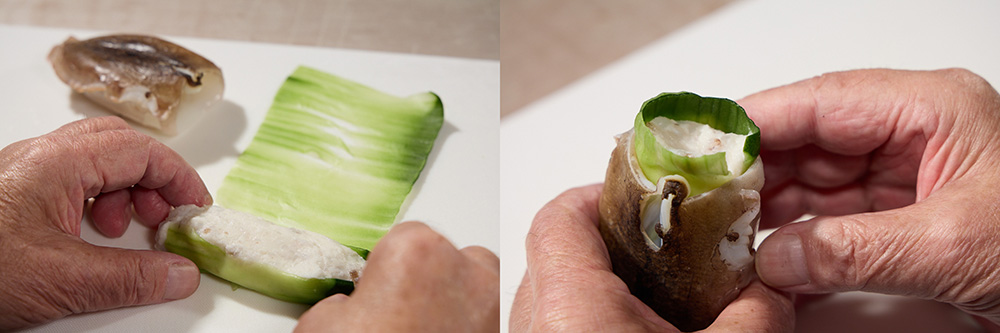
<2種の吉野酢を作る>
- ⑥
- ワタ酢を作る。①のワタを5分蒸して裏漉しする。土佐酢をひと煮立ちさせ、水溶き吉野葛を溶き入れて火を止め、ワタを混ぜ合わせる。
- ⑦
- 淡口吉野酢を作る。淡口醤油・みりんを合わせてひと煮立ちさせる。水溶き吉野葛を溶き入れ、火を止めてから、柚子果汁を混ぜ合わせる。

<仕上げる>
- ⑧
- ⑤を輪切りし、器の真ん中に盛る。⑥と⑦をそれぞれ流し入れ、浜防風をあしらう。

巻針烏賊白扇揚——道明寺粉を詰めたイカ飯風の揚げ物を、淡口天つゆで
先の「ゲソ詰め針烏賊」をそのまま揚げても面白いな、と思ったんやけどね。山芋とろろを道明寺粉に変えて、イカ飯風にしてみましてん。蒸して戻した道明寺粉で霜降りしたゲソをくるんで、胴身に詰めた白扇揚だす。
え? イカと一緒に炊いてこそイカ飯やって? 鋭いご指摘ですなぁ。実は、胴身やゲソを霜降りした昆布だしで道明寺粉を戻して、針イカの旨みを染み込ませてますねんで。白扇揚にするのに卵白を使うから、卵黄が余りまっしゃろ。これを半煉りにして合わせると、黄色く染まって見栄えもよくなりますな。
胴身は揚げると縮むから、塩〆し、脱水させてから使っておくれやす。打ち粉をしたら、ここでもう一工夫。ちょいと香りが欲しかったので、大阪菊菜を湯がいて叩き、卵黄と合わせたものを塗りましてん。先の黄色いイカ飯風をのせ、くるりと巻いてネ。揚げてもほどけないように、海苔で巻くとよろしいな。
輪切りにすると、この断面。一口の中にいろんな風味がおまっさかい、まとめ役には淡口醤油がうってつけや。だしとみりんで、シンプルに淡口天つゆ。大根おろしを添えてネ。ぱらりと散らしたのは、イカ墨パウダー。コレ、なかなかええアイデアでっしゃろ。
巻針烏賊白扇揚のレシピ
【材料(6人前)】
<巻針烏賊白扇揚>
針イカ……500g(2ハイ分)
塩・昆布だし・海苔……各適量
道明寺粉……100g
卵黄……1.5個分
大阪菊菜……1束
小麦粉・卵白・片栗粉・揚げ油……各適量
●淡口天つゆ
│カツオ昆布だし……140ml
│淡口醤油……20ml
│みりん……10ml
大根おろし……適量
【作り方】
<針烏賊を白扇揚にする>
- ①
- 針イカの胴身を開き、甲羅やゲソ付きの内臓を外す。胴身の内側の薄皮を取り除き、隠し庖丁をする。塩をして脱水シートに1時間ほど挟んでおく。墨袋は取っておくこと。
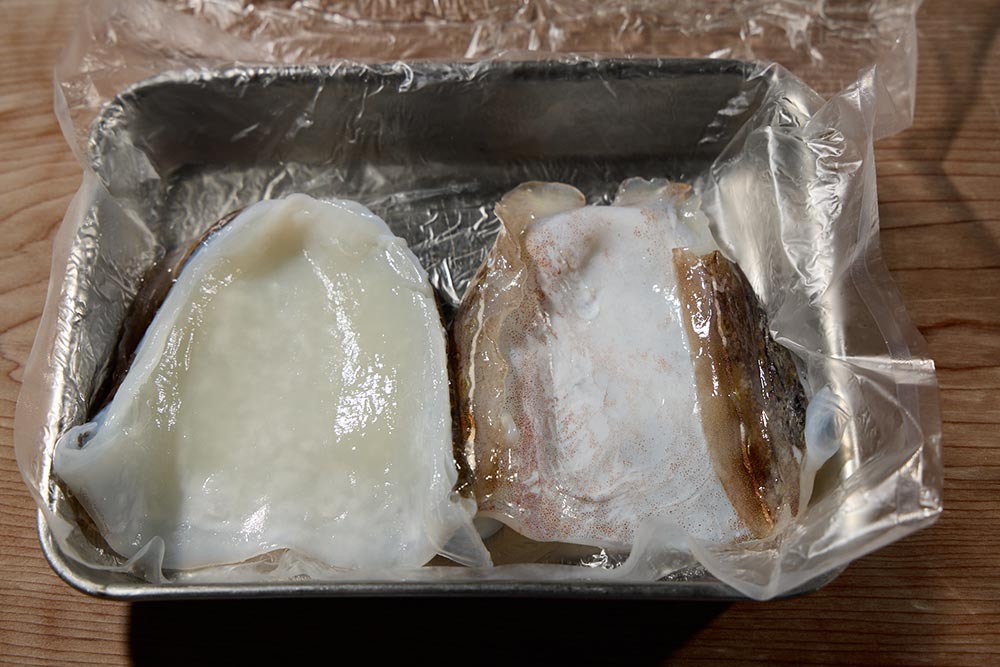
- ②
- ゲソは吸盤を取り、1本ずつ切り離す。①と共に昆布だしで霜降りする。
- ③
- 道明寺粉を②の昆布だし150mlに浸け、10分蒸して戻す。

- ④
- 卵黄1個分を加熱しながら半熟に煉り(半煉り卵黄)、③と合わせる。
- ⑤
- ④を広げ、②のゲソを上下逆にしてのせてまとめる。
- ⑥
- ②の胴身の水気をふき取り、小麦粉で打ち粉をする。大阪菊菜を塩茹でして叩き、卵黄1/2個分と混ぜたものを塗る。⑤を芯にして巻き、皮目に隠し庖丁を入れて海苔で巻く。

- ⑦
- ⑥に卵白・片栗粉・水を合わせた衣を付け、160~165℃の油で白扇揚にし、半生に火を入れる。

<仕上げる>
- ⑧
- 淡口天つゆを作る。カツオ昆布だし・淡口醤油・みりんをひと煮立ちさせる。

- ⑨
- ①の墨袋から墨だけを出し、水気を飛ばすように2分湯煎する。
- ⑩
- ⑦を輪切りにして器に盛る。大根おろしを添え、⑨をかけ、⑧を添える。


超特選丸大豆うすくち吟旬芳醇(左)
国産原料を100%使用。丸大豆しょうゆと米糀の二段熟成で、まろやかな味わいに。400ml。
特選丸大豆うすくちしょうゆ(右)
国産原料を100%使用。淡く上品な色合いと、おだやかな香りで素材を生かします。500ml。
■問合せ:ヒガシマル醤油㈱ お客様相談室 ☏0791-63-4635(受付時間9:00~17:00、土・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇を除く) www.higashimaru.co.jp
フォローして最新情報をチェック!