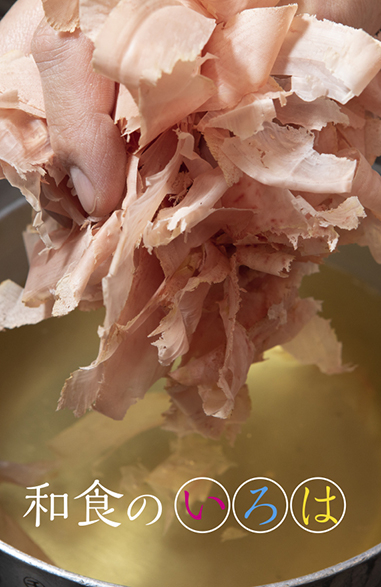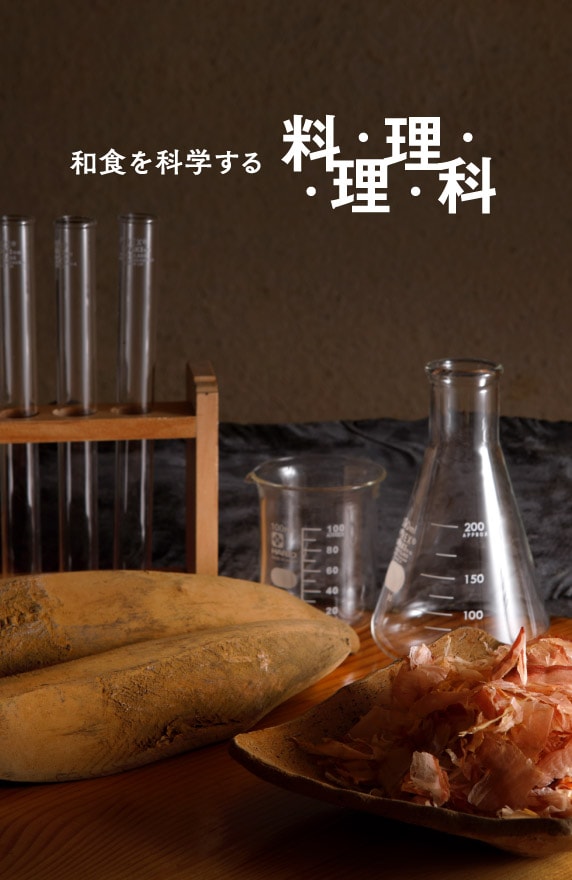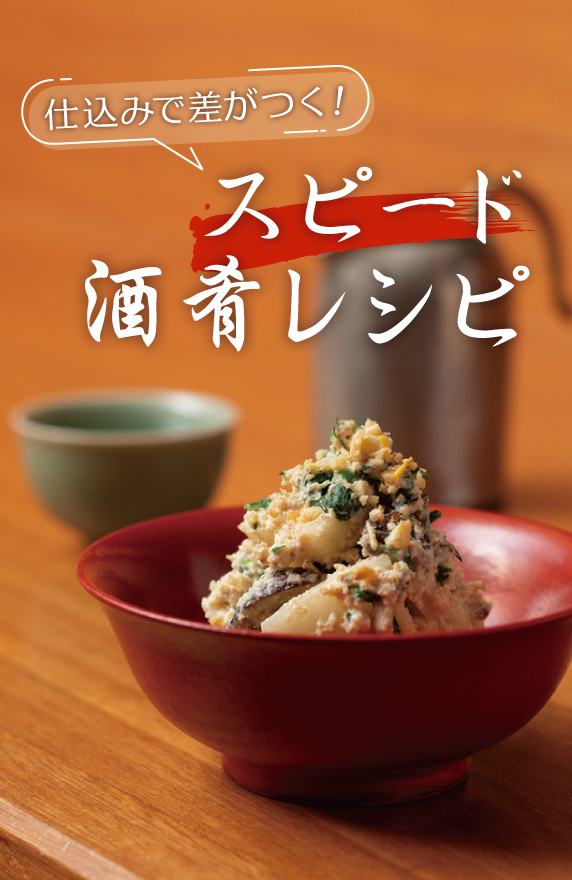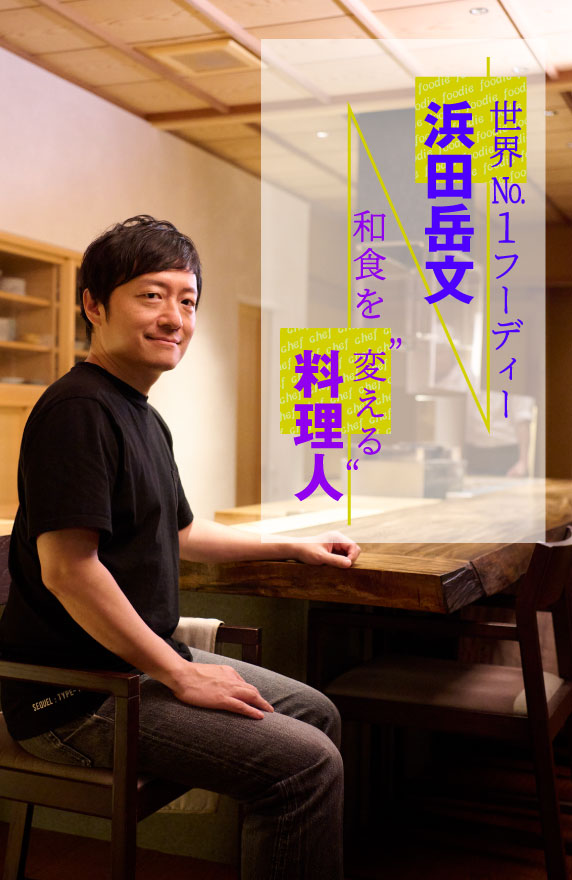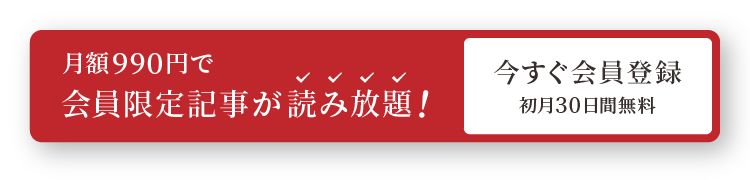×塩鶴るりこvol.2【一問一答】多彩な表現スタイルの背景にあるもの
佐賀県は伊万里市の山中に登り窯を築き、自らも土を掘り、灰から釉薬を作る。磁器も焼けば陶器も焼く。有田で10年、現在の地で唐津焼を始めて36年、両地で積み上げた経験が一つに溶け合う塩鶴さんの作品は、「何人で作ったんですか?」と聞かれるほど、多彩で異なる作風が魅力です。料理人からの人気が高い理由を、石川さんの質問から紐解いていきます。
Q1:なぜ陶芸をやろうと思ったのですか?
 上から時計まわりに白磁の菊の小皿、片口小付、染付唐子小付。
上から時計まわりに白磁の菊の小皿、片口小付、染付唐子小付。
磁器に土もののような揺らぎや厚みがあるのは、どちらのうつわも手掛ける塩鶴さんの個性。
陶芸をやろうと思ったのは高校生の時でした。昔から手先は器用だったので、ものを作る仕事が向いていると思ったんです。できることなら一生飽きずに続けられる仕事をと思い、一人、有田へ行きました。異国情緒のある有田焼に惹かれていたんです。ですから、陶芸のスタートは磁器からでした。
ところが、有田は分業制。ろくろはろくろだけ、赤絵は赤絵だけ。何もかも自分でやりたい私は、ろくろ仕事をしながら、染付の工房や赤絵の工房にも習いに行きました。8年目ぐらいから週末は唐津焼の仕事を見せてもらうようになり、1年半ほどして有田の仕事を辞めて唐津焼を始めることにしました。
基本の技術を学ばせていただいた有田には感謝しています。その土台があって初めて創作ができると思っています。何から何まで一人でやろうと独立したのですが、実は、窯焚きの経験は2回しかなくて…。初めて一人で窯焚きした時は、何とか窯に作品を詰めることはできたのですが、火がつかなかった。薪の組み方を知らなかったんです。それくらい無謀なスタートでもありました。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!