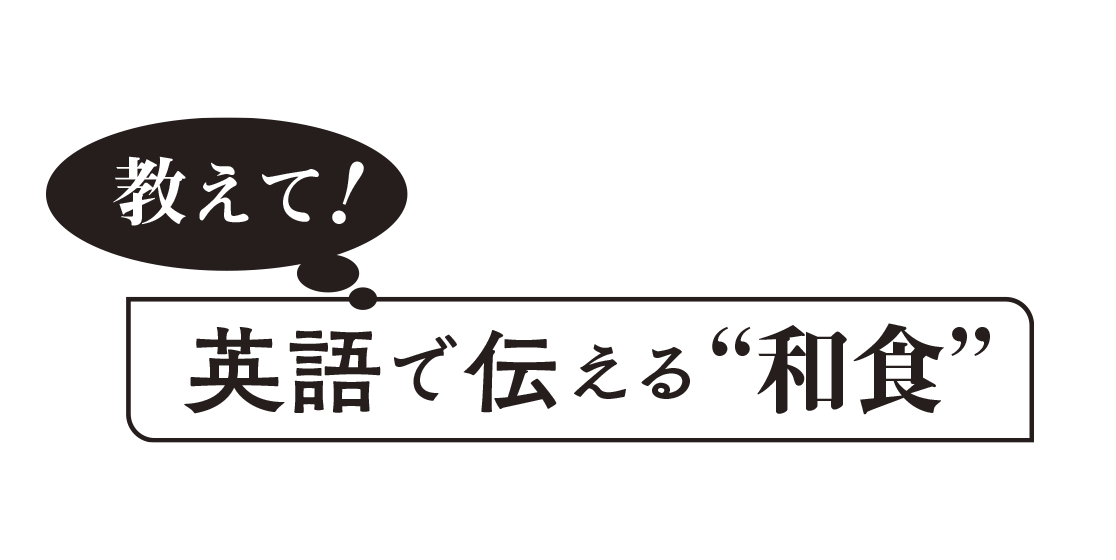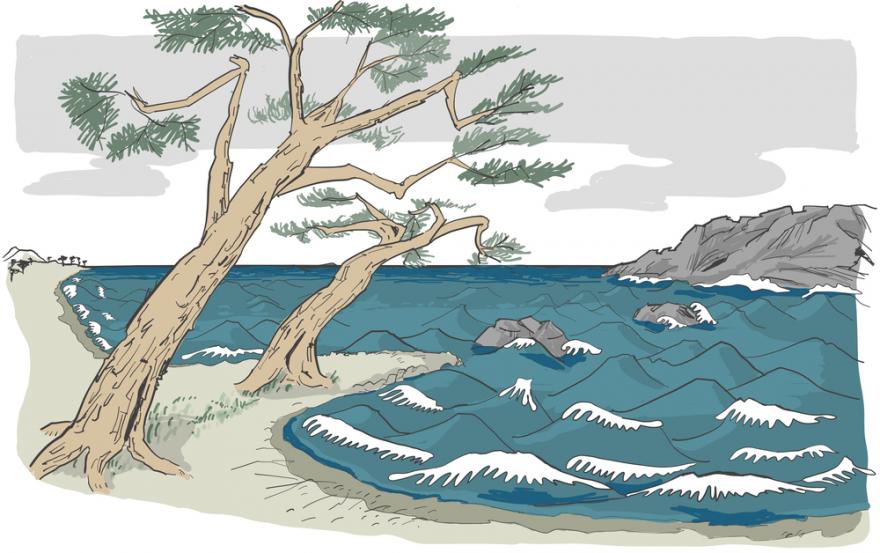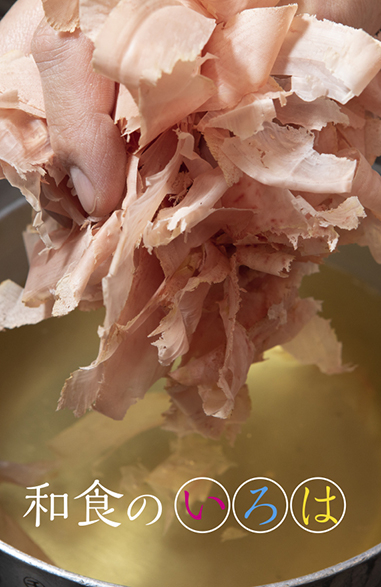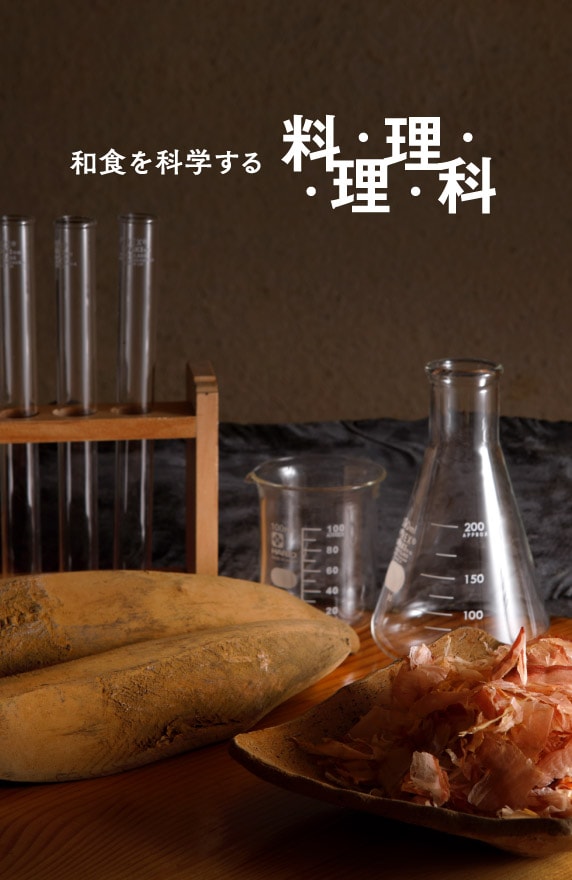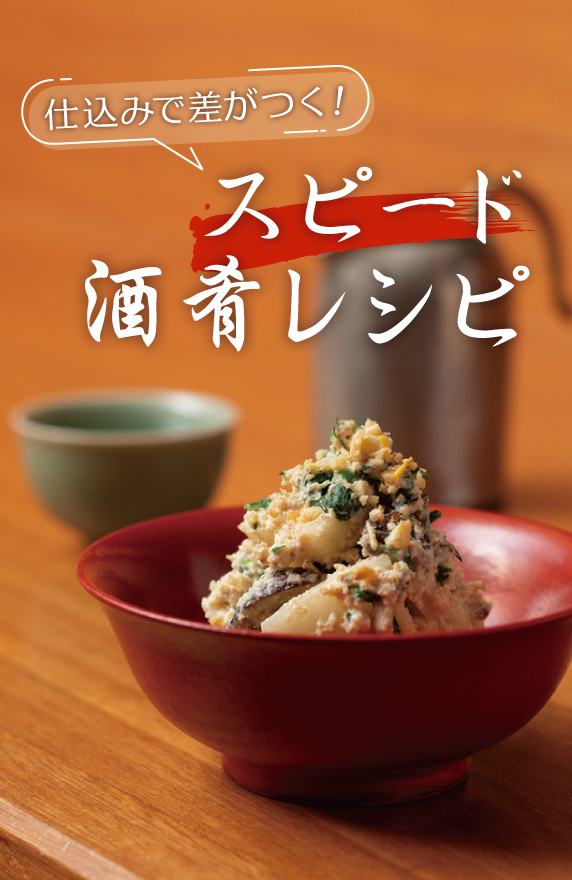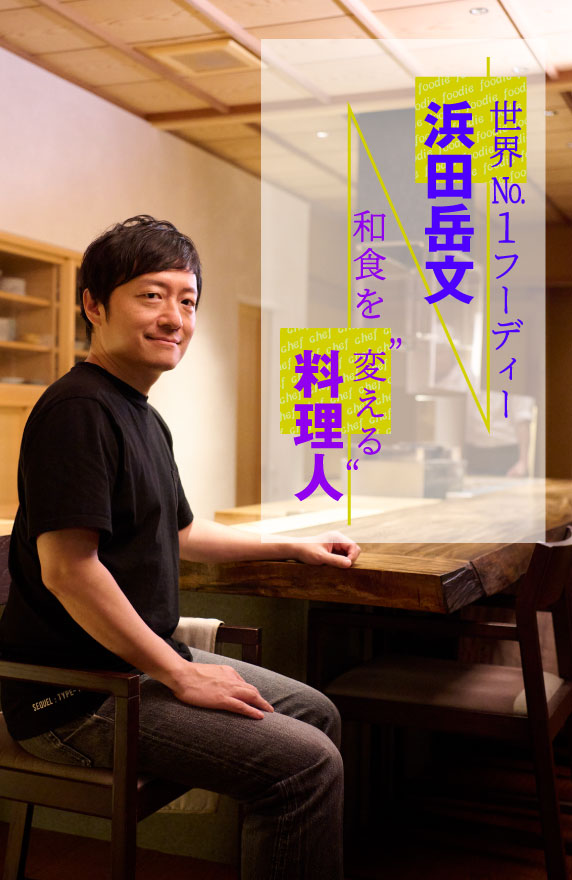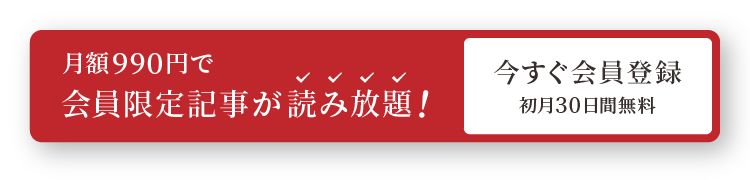【7月】こんな時、英語でなんと言う?
7月は七夕の節句があり、さらに関西では京都の祇園祭や大阪の天神祭など、夏を象徴するイベントが開催されます。祭にちなんで食べられる鱧も関西の名物。七夕にまつわる話や、鱧の骨切り、日本ならではのマナーなど、どう伝えるべきなのか。万博の開会も伴い、依然として訪日外国人は増え続けるいま、日本の食材や伝統的な文化を知ってもらえる絶好の機会です。7月にまつわる質問を中心に『京料理 たか木』の髙木一雄さんに投げかけ、いかに英語で説明するといいのか、お教えいただきます。
髙木一雄さん:1972年、大阪生まれ。料理教室を営む母の影響により、料理の道へ。大学在学中に老舗料亭『大和屋』で修業を始め、『京大和』でさらに研鑽。2005年、兵庫・芦屋に『京料理 たか木』をオープンする。バンコクやモルディブの日本料理店の監修や、海外や国内のシェフとのコラボ、商品開発なども積極的に手掛ける。イギリス留学の経験もあり、柔軟で、ワールドワイドな視点の持ち主。
文:奥田眞子
鱧の骨切り、どう伝える?
-
質問者

- 鱧の骨切りをすると、興味をもたれて「何をしているの?」と尋ねられます。英語でどのようにお伝えするのがよいでしょうか?
-
髙木

- まず、英語で鱧は「pike conger」ですが、僕は「hamo」と言っています。
中国や韓国では食べられるようですが、他の国の方にとっては見慣れないので「pike conger」と言っても「ああ!あの魚ね」とはならないと思います。
だから、まず鱧は関西で親しまれている魚で、特に夏の京都の名物だと説明してあげるといいですね。「Hamo is often eaten in Kansai ,and is especially known as a specialty of Kyoto.」です。
骨切りは「Cutting bones」で伝わりますが、小骨が多いことや、骨切りという日本ならではの技術があることなども合わせて説明してあげると親切です。「Hamo has many tiny bones, so it needs a special cutting techniques called Honekiri, which is unique to Japanese cuisine.」
また、庖丁を見せて骨切り専用だと教えてあげるのも面白いですよ。「This knife is specifically for cutting hamo bones.」
<補足>
鱧は食感が楽しい焼き霜造りや天ぷら、見た目が美しい薄造りなどが特に海外の方に好評という印象があります。
この記事は会員限定記事です。
残り:2876文字/全文:3955文字
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!