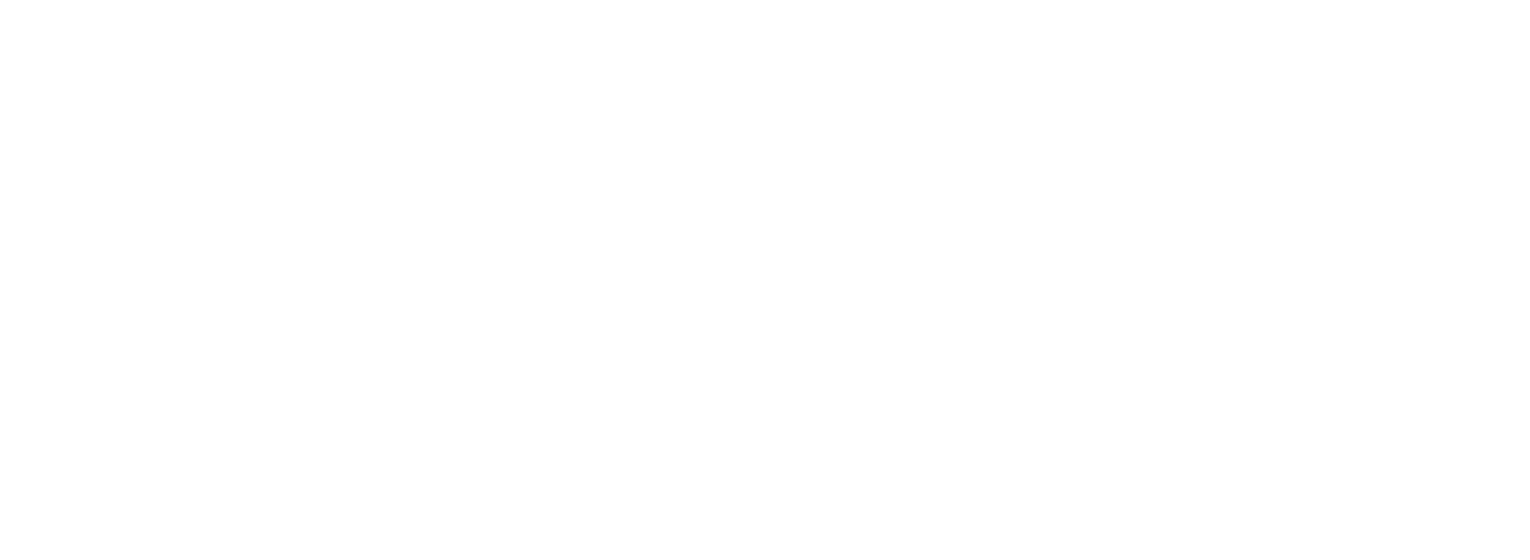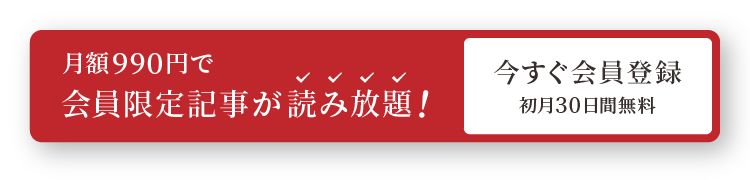1日の気温差20℃。厳しい環境が生む酸味と甘み
「昨日は満月の大潮で、トマトも喉が乾いちゅうかもしれんと思って、勇気を出して水をやりました」。
こう話すのは、「てっぺんとまと」の名称でトマトを栽培する西森常晴さん。標高830mの山でトマトをハウス栽培し始め、今年で28年目を迎える。
トマトは乾燥を好み、強い日差しによって育つとされながら、高温に弱いという特徴がある。また、多雨多湿に弱く、病害におかされやすいことから、管理が難しい植物とも言われる。
中でも「高糖度トマト」として甘みを持たせるには、極限まで水やりを制限することが重要になる。それによりトマトの実に栄養が蓄積していき、甘みとなるためだ。
「水やりは1週間に1度、5〜10分と短時間で。植えた直後、2日間は水をたっぷりやりますが、その後1カ月は、一滴も水を与えません。水の量はその日の気温や天候などを踏まえて調整しますが、この塩梅が難しい。だから水をやる時は、エイッという思い切りと覚悟が必要ながです」。
また、新月に竹を伐採すると、丈夫で腐りにくい竹材になると言われるように、トマトの成長にも月のリズムが影響するという。
「満月前後は、成長の動きが活発になって喉が乾きやすくなる。大潮の時には害虫が産卵孵化(ふか)して虫が増えるし、月のリズムは植物とも密接に関わっちゅうと思います」。
てっぺんとまとは甘いだけでなく、酸味もしっかりあるのが大きな特徴だ。一般的に糖度計で10度以上だと、食べた時にしっかり甘みを感じるトマトになるとされる。てっぺんとまとの糖度が10度になるのは、収穫時期が終わる10月下旬頃。収穫が始まる6月下旬〜10月中旬頃の糖度は8度強と、一般的な冬春の高糖度トマトに比べると低い。なお、普通のトマトの糖度は約5度だ。
「てっぺんとまとの味は、この立地と環境こそが作るとも言えます。山のてっぺんで昼夜の気温差が20℃近くなる環境は、トマトの原産地である南米のアンデス高原の気候とよく似ています。この厳しい環境がトマトの糖度と酸味を増し、味を濃厚にしてくれるのです」。
「地の利」✕「土作り」で不可能を可能に
トマト栽培において、「人間にできることは、ほんのわずか」だとし、“地の利”を美味しさの秘訣の筆頭に挙げる西森さんだが、栽培へのこだわりは並々ならぬものがある。
特に土作りは、「地力に勝る技術なし」をモットーに、微生物と酵素を応用した「島本微生物農法」を基本とし、土の力を強くするために試行錯誤を重ねてきた。
次のシーズンのトマトの質を落とさないため、毎年10月下旬には収穫を終え、土作りを開始する。ハウスの天井を開放し、太陽、雨、風を取り入れて、今まで閉じ込めていた土を自然に返すことからスタート。雨水はカリ(カリウム)が過剰となった土を回復し、地力をつけてくれる。
そして、トマトの残渣(ざんさ:濾過をした後に残ったカス)とサトウキビの葉からできた土壌改良剤を浅くすきこむ。ハウスの天井を開放する→雨水が入る→土ごと発酵させるという一連のサイクルが、次のシーズンへの土作りの土台になる。
連作障害への対策も欠かさない。トマトの間に1万本の枝豆を植えたこともあるが、今はトマトの収穫時期が終わると、緑肥作物のライ麦を植える対策に落ち着いた。これに加え、米ぬか・有機土壌改良剤・にがり・魚粉・木酢などが、土作りの基本となっている。
「連作障害を防ぐのも作物の味を作るのも土。いろんな本を読んで実践してきたけど、結局は、昔のやり方に沿うのが一番じゃないかなと思うようになりました」。
弱る寸前に味ができる“スパルタ農法”
西森さんは、夏から秋にかけて味わえるフルーツトマトの先駆者だ。栽培を始めた28年前は、誰もが「夏のフルーツトマトなんてできるはずがない」と首を横に振ったという。夏の酷暑の中で、甘さを作るのは困難とされていたためだ。
農業は全くの初心者だった西森さんだったが、冬春にフルーツトマトを作っていた親戚らの応援もあり、挑戦に踏み切った。
1年目は、右も左も分からないことだらけ。さまざまな本を読んで取り組むも、水やりの見極めがたいそう難しい。高糖度トマトは、茎がタバコ程度の太さが良いとされる中、気づけば一部は、楊枝ほどの太さになってしまった。
「全部がダメになるかも」と落胆しかけていたところ一気に花が咲き、みるみる甘酸っぱい実を付けた。トマトは過酷な環境の中で、弱る寸前に“味”ができること、いわば“スパルタ農法”が実を結ぶと分かった瞬間だった。
2年目からは、どんどん売れるようになり、値段も右肩上がりに。あまりの売れ行きに、農協や周囲も舌を巻いたという。
「値段が上がったのは、味はもちろんですが、やはり夏の高糖度トマトの希少性でしょう。作物の値段は、需要と供給のバランスで決まることを実感しました」。
最初の数年は、農協を通じて「ぴゅあトマト」として販売していたが、丹精を込めて育てても生産者の個人名が出ず、他と区別がつかない状態で売られることに疑問を持つようになった。毎日、決められた時間に間に合うよう、山から降りて納品に出向くことも、夫婦2人で始めた農家には大きな負担だった。
かくして、「てっぺんとまと」の名前で、自分たちで直接売り出すことに。自分たちのトマトに、揺るぎない自信があったからこそ決断できた道だ。今では西森さん夫婦を含め、総勢10人ほどで栽培や出荷を行っている。
「てっぺんとまと」の成功を見て、トマト農家に転身する人も出てきて、現在は近隣の5箇所で栽培されるようになった。
「人里離れた山やけど、今はシーズンになると毎日30台近くの車が行き来する。商売がうまくいったから仲間が増えた。嬉しいです。頑張って続けて、町の雇用も守らんとね」。
今年も“お墨付き”をもらって出荷スタート
甘さと酸味が際立つ「てっぺんとまと」は和食やイタリアンなど、ジャンルの垣根を超えて料理人に愛されている。
「甘さ一辺倒じゃなくて、酸味がしっかりあるのが良いと言うてくれます」。
生でももちろん良いが、火を通すと、また違った味わいやコクが引き出される。西森さんのおすすめはトマトソースにして、いろんな料理に活用すること。湯を沸かして3秒ほどトマトをくぐらせ、皮をむく。それをミキサーで液状にし、鍋でコトコト温める。
「製氷皿で凍らせておくと長期保存もできて便利ですよ」。
「トマト作りは、生涯のテーマ」という西森さん。毎年、研究と実践を重ねながらも、「まだまだ分からんことがたくさんある」と言う。糖度計で甘さを測る時は毎回、全身に緊張感が走る。取材時も、高糖度の目安「8度」を超えたのを確認し、心から安堵した表情を見せていた。
「けんどね、味の確認に一番いいのは、子どもの反応。子どもが喜んで食べてくれたら本物やと思う。だから毎年、子どもの反応を見ることにしちゅうがです」。
今夏も、子どもからの“お墨付き”を早々に得て、全国へと出荷している最中だ。山のてっぺんでの挑戦は、輪を広げながら続いている。




【住所】高知県吾川郡仁淀川町名野川440-8(事務所)
【FAX番号】0889-36-0538
【営業時間】9:00〜16:00
【定休日】なし
【HP】https://teppentomatoniyodo.wixsite.com/tomato
【Instagram】https://www.instagram.com/teppentomato_niyodo/
【Facebook】https://www.facebook.com/teppentomato
フォローして最新情報をチェック!